落語ってなに?
落語は、日本に古くからある、お話でみんなを楽しませる “わざ” のひとつ!
その “わざ” をもっている人のことを落語家、または、噺家とよんでいます。
金原亭世之介ししょーも落語家です!
金原亭世之介ししょー
落語には、楽しいお話や、心がふるえるお話がたくさん!
落語はキャラクターのお話のやりとりだけで、ストーリーが進みます。
これは、世界でもめずらしいものなんです!
なので、落語は日本にしかない、言葉のアートといわれていますよ!
落語をする、世之介ししょー
落語家さんは、たくさんのお客さまの前で、ひとりだけで高座に座ります。
そして、扇子と手拭いだけをつかってお話します。
ほかには何も持ちません!
おもしろいお話をする世之介ししょー
落語家さんは、じぶんひとりの力で、みんなを楽しませるプロなのです!
落語ってむずかしい?
落語はかんたん!!
むずかしいルールはありません!
なんと!落語にチャレンジしている、お友だちもいますよ!
それでも、やっぱりむずかしそう?
では、知っていると落語博士になれる「まめちしき」をお教えましょう!
じつは、落語のお話は3つに分けることができるんです!
……いかがでしょう?
もっと落語のことが知りたくなってきたでしょう??
それでは、もーっと落語博士になれる、とっておきの情報をお教えましょう!
落語のアイテム
落語を演じる落語家さんのまわりには、いろんなアイテムがあります!
アイテムの名前を知れば、もっと落語がたのしくなること、まちがいなし!
 高座
高座
落語家さんが落語をしたり、芸人さんが芸をする舞台のこと。
お客さまがいる客席から一段高くなっています。
落語家さんが座る座布団もおいてありますよ!
赤い布がしいてあることもあります。この赤い布を「毛せん」といいます。
高座といえば、「高座にかける」というかっこいい言葉もあります!
落語家さんが落語のお話をお客さまの前でやることを「高座にかける」というのです!
 めくり
めくり
いま高座に出演している落語家さんや芸人さんの名前が書いてある紙です。
高座においてあります。
ペラペラめくるものや、板を入れかえるものなど、いろんなタイプがあります。
ペラペラめくるタイプのめくり
『ぐっどすとっく落語会』Goodstock Tokyo 2024年8月6日 より
 扇子と手拭い
扇子と手拭い
みなさんご存知!扇子と手拭いです。
手拭いの模様は落語家さんによってさまざま!
手拭いには、落語家さんに伝わる、きまった “たたみかた” があるそうです!
ヘンな “たたみかた” では、すばらしい落語はできないのだそうです。
“たたみかた” は師匠によってさまざま。
それが代々弟子にうけつがれてゆきます。
手拭いの “たたみかた” からも、「ひとを楽しませるプロ」の心を感じますね!
落語の歴史
ふる〜い歴史を感じる落語!
みなさんは落語がいつからあるのかご存知ですか?
落語の歴史は、戦国時代までさかのぼります。
たくさんの武将が戦いをくりひろげていた時代です!
そのころに、落語っぽいことをはじめたのが、曽呂利新左エ門という人といわれています。……ちょっとヘンな名前ですね。
曽呂利新左エ門
国立国会図書館デジタルコレクション
『曽呂利新左衛門伝』
(天保面ノ半 著,柾木正太郎,1879年) より一部抜粋
豊臣秀吉に仕えたといわれていて、その頭のよさは逸話として、いまでも語りつがれています。
江戸時代になり、関西では、露の五郎兵衛が、道ばたでおもしろい話などをしてお金をもらう辻噺をはじめました。
そうやって、おおくの人たちが落語の元をつくっていったのです。
いまの落語のかたちになったのは、江戸時代のおわり(幕末)から明治時代にかけて。
三遊亭圓朝という大名人が活やくし、落語をいまのかたちに完成させました!
三遊亭圓朝
国立国会図書館デジタルコレクション
『円朝全集』巻の十』
(三遊亭円朝(他) 著,春陽堂,1927年) より一部抜粋
落語はどこでやってるの?
みなさんも、本物の落語をみたくなってきましたか?
それでは落語をみられる場所をお教えしましょう!
落語をみたいなら、寄席にいくのがオススメ!
寄席は、落語や、ほかのさまざまなを芸が演じられている場所のこと。
そのなかで、まいにち落語をやっている場所のことを定席といいます!
東京にある定席は4つ!

上野鈴本演芸場

新宿末廣亭

浅草演芸ホール

池袋演芸場
そのなかで、一番古い定席が新宿末廣亭です!
新宿末廣亭
新宿末廣亭は、明治30年にたてられた寄席。
2回の火事で燃えてしまいましたが、昭和21年にいまの場所に建てられることになりました。
東京の定席のなかで、木でつくられているのはここだけなのです!
でている人がかいてあります!
新宿末廣亭のなか
チケットは寄席の入り口にある受付で買うことができます。
チケットのこと、また、チケット・切符売り場のことを「テケツ」ともいいますよ!
新宿末廣亭のテケツ
 寄席を楽むコツ
寄席を楽むコツ
寄席は、身近な伝統芸能です。むずかしいことはな〜んにもありません!
でも、ちょっと知っておくと、もっと楽しめる「まめちしき」がいくつかあります。ここでは、そんな「まめちしき」をご紹介しましょう!
-
 マナーを守ろう
マナーを守ろう
寄席はたくさんの人があつまるところ。「マナー」を守って、楽しんでくださいね。
-
会場のなかで走ったり、大きい声で話さない。
-
開演中はお静かに。
開演中は、おしゃべりをしないようにしましょう。
ただし、落語や演目が楽しくて笑っちゃうのはOKです!
-
開演中は席を立たないようにしましょう。
席を立つと、うしろの人が見えなくなってしまいます。
開演中に立たなくてもいいように、トイレは先にすませておくか、仲入りという休み時間にすませておきましょう。
-
開演中は、スマホ・ゲームはOFFにしましょう!
-
 どんな服で行く?
どんな服で行く?
寄席は、特別な服を着てこなくて大丈夫!
いつも着ている服で楽しんでください!
-
 どの席に座る?
どの席に座る?
定席は、空いている席ならどこに座ってもOK!
ただし、特別な公演では席が決まっていることもあるので、わからないときは受付できいてみてくださいね。
さて、寄席や劇にでる人たちが準備をしたり、休んだりするところを楽屋といいます。
いつもは、お客さんが見ることができない場所ですが、今回はとくべつに、みなさんにお見せしましょう!
新宿末廣亭の楽屋
楽屋のまんなかに、なにか丸いものがありますね?
これは火鉢!
なかで炭を燃やして、あたたまったり、お湯をわかしたりします。
世之介ししょーもあたたまっていますよ!
うしろに太鼓もみえますね!
落語家さんや寄席にでている芸人さんには、一人ひとりにテーマソングがあります。
そのテーマソングのことを出囃子といいます!
出囃子の太鼓は、落語家さんになるために修行をしている前座さんが演奏します!
そして出囃子の三味線は、お囃子さんが演奏します!
太鼓を演奏する前座さん
お囃子さん
新宿末廣亭の楽屋には、落語にまつわる “めずらしいもの” もおいてあります。
ぞろぞろの“わらじ”
“わらじ” がつるされていますね!
“わらじ” は、わらでできた “はきもの” のこと。むかしの “くつ” です。
落語のお話のひとつに『ぞろぞろ』というお話があります。
お店につっていた “わらじ” が、売っても売ってもたくさん生えてきて、お店が繁盛する、というお話です。
そんなふうに、新宿末廣亭も繁盛しますように、という願いをこめて、“わらじ” がつるされているそうです!
落語家になるには?
落語をみたら、落語家さんになりたいお友だちもいるかもしれませんね。
落語家さんになるにはどうすればよいのでしょう?
プロの落語家さんになるには、きびしい修行をしなければなりません!
世之介ししょーも、きびしい修行をして、落語家さんになりました。
むかしのししょー
師匠とよばれる落語家さんになるには、4つのレベルをクリアしなければなりません。
東京と関西では、すこしちがうところがあります。
今回は、東京の落語家さんについて、みていきましょう!
落語家さんになるには、師匠とよばれるに落語家さんに弟子入りをしなければなりません。
弟子入りにテストはありませんが、ほとんどは「ダメだ」といわれてしまいます。
それでも弟子になりたい!と一生けん命おねがいをして、やっと弟子にしてもらえるのですっ!
世之介ししょーも、師匠である十代目 金原亭馬生師匠に、何度も「ダメだ」といわれたそうです。
それでも、どうしても落語家さんになりたくて、何度もおねがいをして弟子入りをゆるしてもらったそうです。
十代目 金原亭馬生師匠とむかしの世之介ししょー
 前座見習い
前座見習い
弟子入りすることを入門する、ともいいます。
まず入門すると、前座見習いとして1年半ほどはたらきます。
ここから、まいにち、師匠のところへ通ってお仕事をおぼえます!
落語をおぼえるだけではなく、着物のたたみ方、手拭いや扇子のつかい方、たいこのたたき方、お作法などなど……。
たくさんのことを勉強します!
師匠の荷物もちや、おうちのおそうじ、お茶だしもします。
馬生師匠について
荷物もちをする、むかしのししょー
 前座
前座
師匠のもとで、たくさんのことをおぼえたら、つぎは前座さんとして、寄席ではたらきます。
前座見習いのときからつづけているお仕事もしながら、寄席でもはたらくので、とってもたいへん!
高座では、座布団をひっくりかえしてととのえたり、めくりをめくります。
これを「高座返し」といいます。
高座返しをする前座さん
そして、楽屋にいるたくさんの師匠たちのおてつだいもします!
師匠たちの着物もたたみます!
 二つ目
二つ目
前座さんからかぞえて “ふたつめ” なので、二つ目とよばれているそうです。
前座修行がおわり、まいにち師匠のところへ通うことや、師匠たちのおてつだいもなくなります。
紋付の着物や羽織、袴を着られるようになって、自分のテーマソングである出囃子をもつことができます!
……とはいえ、ここからが本当の落語家としてのスタートライン!
落語だけではなく、日本舞踊、俳句、歌など、いろいろなお稽古を、まいにちつづけるのです。
 真打ち
真打ち
真打ちは「師匠」とよばれる落語家です!
真打ちは弟子をもつことがゆるされます。
そして、寄席でさいごの “トリ” をかざることができる存在です!
もちろん、ししょーも真打ちですよ!




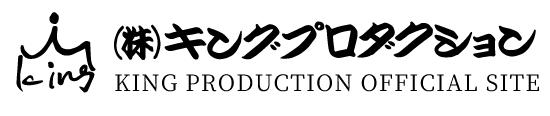







 高座
高座













 寄席を楽むコツ
寄席を楽むコツ
 マナーを守ろう
マナーを守ろう










